先生は信頼できる大人でいてほしい 茂手木涼岳さん(後編) #知りたいを聞く
教育話題

社会応援ネットワーク
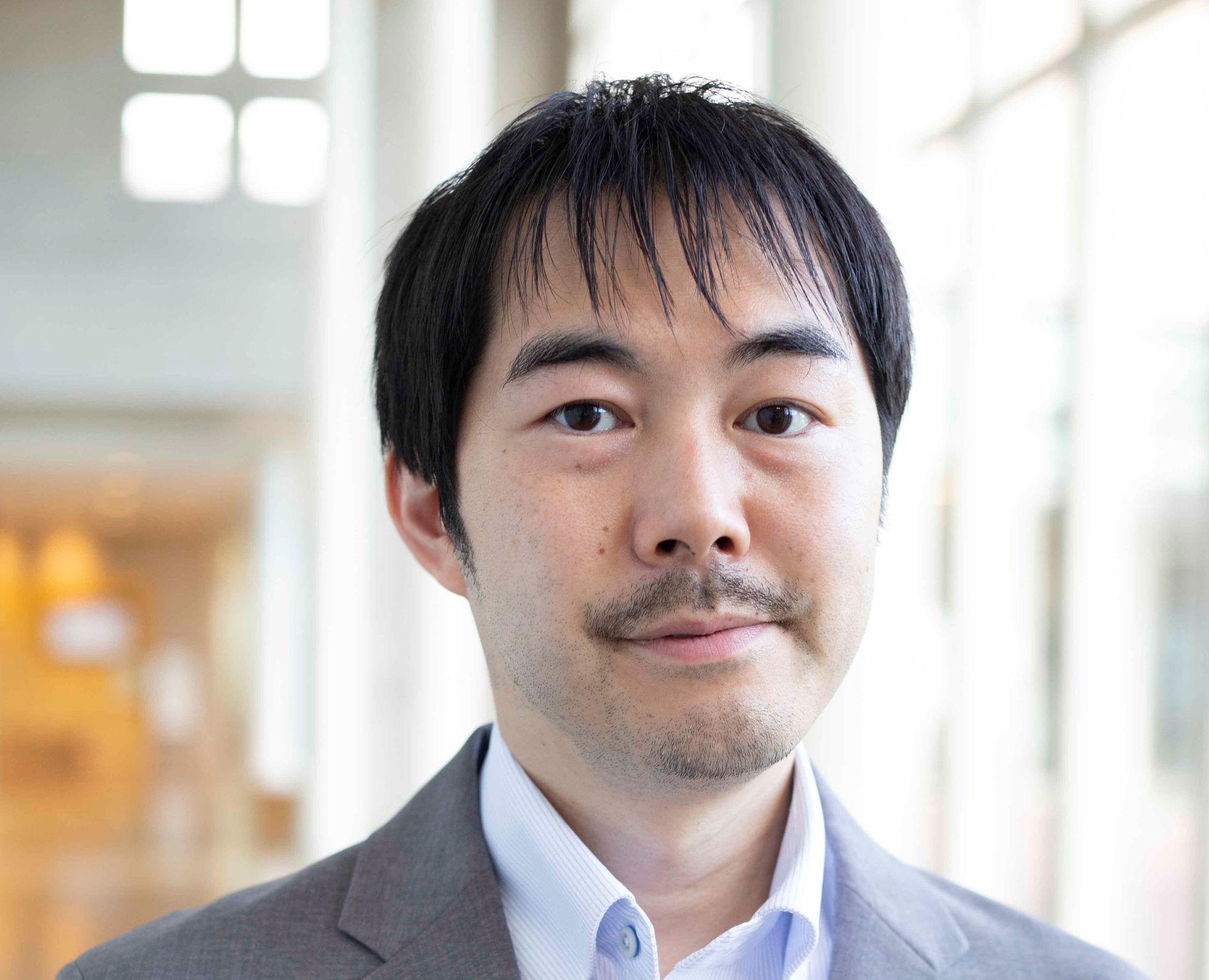
不登校となっている小中学生が30万人に迫る現状をどう考えるか。今回の「#知りたいを聞く」は、不登校で苦しむ当事者や保護者の声を発信し、支援するメディア「不登校新聞」の編集長・茂手木涼岳(りょうが)さんへのインタビューの後編です。学校現場として不登校問題にどうアプローチするべきかや、学校・行政とフリースクールを含む民間事業者との連携などについて語っていただきました。
茂手木涼岳さんへのインタビューの前編はこちら
1981年生まれ。図書館でのアルバイトと会社員を経て、不登校新聞社で事務アルバイトとして働き始める。その後、編集スタッフに。2022年に3代目編集長に就任。小学生の娘の父でもある。
――子どもが学校に行き渋るなど、不登校の兆候を見せた場合、学校ではどのような対応を取るのでしょうか。
対応は学校によって違います。一部では、不登校対応のマニュアルがある学校もあります。例えば、3日休んだら家庭訪問する、1週間で対策チームを立ち上げるなど、対応をマニュアル化しているのだとか。
ひと昔前は「何としても学校に来させる」といった考えが主流でしたが、教育機会確保法や文部科学省の通知などによって、また、スクールカウンセラーが配置されたことによってメンタルヘルスへの理解が広がったこともあり、「登校刺激」一辺倒の対応は、以前ほど多くありません。
ただし、先生個人の不登校への理解度や考え方によっても対応方法は違うはずです。先生によっては、かつてのように不登校の子どもを無理にでも学校に連れて行こうとするといった指導もあるようです。

社会応援ネットワーク
全国の小中学生向けの『子ども応援便り』編集室が、2011年東日本大震災時、「メッセージ号外」を発行したのを機に設立し、文部科学省等の委託で被災地向けの「心のケア」の出張授業を開始。以降、全国の小学校に『防災手帳』を無料配布するなど、学校現場からの声に徹底して応え、心のケア、防災、共生社会等の出張授業や教材作り、情報発信を続ける。コロナ禍では「こころの健康サポート部」サイトを立ち上げた。書籍に『図解でわかる14歳からのストレスと心のケア』『図解でわかる 14歳からの自然災害と防災』(太田出版)など。












